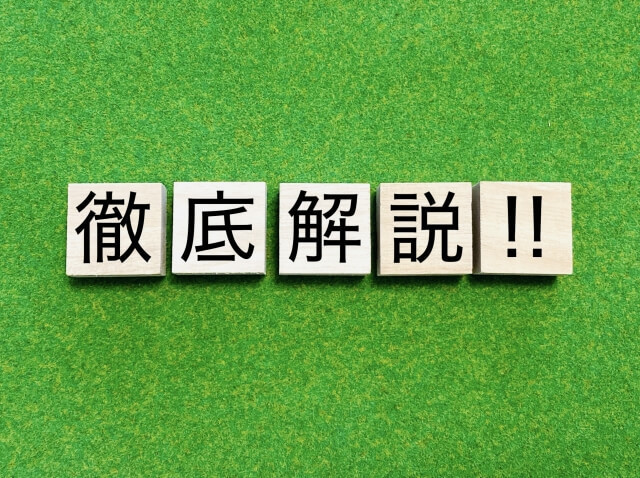司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区高島2-14-12 ヨコハマジャスト2号館5階
(横浜駅東口より徒歩3分)
TEL:045-328-1280
自己破産とは?

自己破産とは「支払い責任が免責される」ものです。
民間への負債は、自己破産が認められれば、支払いを0にできます。
一方、税金や国民健康保険の滞納分、交通違反の罰金など、公的な支払いは免責されません。
また、子供の養育費、交通事故の相手方への損害賠償債務など、一身専属的な権利も自己破産では免責されません。
自己破産の申立ては、ご自身の住所地を管轄する地方裁判所に行います。
手続きには、数か月(同時廃止)~1年(管財事件)程度は要するのが一般的です。
目次)自己破産の仕組み
自己破産が認められる(免責される)ためには、以下の条件を満たす必要があります。
・支払不能であること
・免責不許可事由に該当しないこと
上記の条件を満たし、「破産を認めるのが相当」と裁判官が判断した場合に、自己破産は認められます。
支払不能について
支払不能とは「今ある負債を自力では返済できない」状態を指します。
これは、申立人の主観で判断するのではなく、客観的な判断になります。
例えば、「支払いがきついから」「返済するのに疲れた」といったものは主観なので認められません。
収入から一般的に必要な生活費を差し引いて、その残額で返済を続けられるか?といった客観的な基準で判断を行うということです。
簡単目安としては、現在の借金総額を36で割り、毎月その金額が支払えなければ、支払不能と言えます。
免責不許可事由とは?
自己破産を申し立てて支払いを免れることを、「免責」と言います。
この免責が認められないケースは、「免責不許可事由」と言って、破産法で定められています。
免責不許可事由の代表的なものとしては、以下の通りです。
・浪費が疑われること
・偏波弁済が行われていること
・財産隠しが行われていること
・破産手続きに協力的でないこと
・1度破産の免責を受けてから7年を経過していないこと
なお、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所が相当と認めるときは「裁量免責」によって、自己破産が認められます。
自己破産を申し立てた場合、その手続きは大きく分けて下記の2種類に分けられます。
・同時廃止事件(財産などもなく簡易な破産)
・管財事件(20万円以上の財産所持や浪費などが疑われる場合)
同時廃止事件について
同時廃止事件は、「破産開始と同時に破産手続きを廃止する」という意味を持ちます。
一見すると理解が難しいかもしれませんが、「破産の申立に問題はないので、すぐ破産手続きを終わらせます」といった主旨で、簡易な破産手続きになるものです。
浪費が疑われない、財産価値があるものを所持していないといったケースでは、同時廃事件になります。
管財事件とは?
・高額な財産をがある場合(20万円以上の価値があるもの)
・非常に大きな浪費などが認められる場合(株やFXの損失なども含みます)
・財産隠しの可能性がある場合
このようなケースでは、管財事件となります。
管財事件では破産管財人が選任され、破産に至った借入状況や現在の財産について、時間をかけてじっくりと調査が行われます。
分かりやすく言うなら、同時廃止事件よりも慎重に進められる破産手続きです。
管財事件では、同時廃止事件よりコストがかかり、デメリットもあります。
まず、破産管財人の選任費用が20万円~30万円ほど発生(裁判所によって異なります)します。
また、郵送物が破産管財人の管理におかれ、一定期間自宅に郵送物が届かなくなったりもします。
自己破産をする場合、申立て時に所有する財産で20万円以上の財産は残せません。
この財産には、現物としての財産の他、債権(将来手にするお金)も含まれます。
現物の代表的なものは、自宅や車やバイク、高級時計・宝飾品などです。
債権の代表的なものが、保険の解約返戻金や、退職金などです。
破産と解約返戻金
「保険の解約返戻金」も、みなし財産とされます。
仮に、今解約したら解約返戻金が20万円以上ある場合には、換価対象です。
保険を解約しないこともできますが、その場合には、解約返戻金にあたる金額は自身で捻出し、裁判所に納める必要があります。
破産と退職金
「将来もらえるはずである退職金」も推定財産となります。
ただし、在職中の場合には、退職金支給見込額の1/8が現在の財産とみなされます。
例えば、退職金見込額が160万円ならその1/8は20万円。この場合には、20万円以下であるため、何も問題はありません。
退職はしたが退職金を受け取っていない場合、この場合は1/4額が評価となります。
すでに退職をして、退職金を受領した場合にはその全額が財産対象です。
自己破産は返済の責任が無くなりますが、その分デメリットも多くあります。
こうしたデメリットを受け入れる代わりに、支払いの責任が無くなると思ったほうが良いでしょう。
官報掲載による個人情報の流出
近年では、官報はインターネットでも閲覧できるようになっています。
そのため、以前より容易に第3者が確認できるようになっており、破産者マップなどの事件が起きている点には注意したほうが良いでしょう。
信用情報への事故情報
いわゆるブラックリストというものです。
ブラックリストになると、クレジットカードを利用したかったり、ローンを組みたくても、審査に通らなくなります。
一生続くというわけではなく、免責を受けてから5年はこの状態が続きます。
資格制限
自己破産には資格制限という制度があります。
一定の資格を使った仕事は、破産手続き中はできないことになっています。
保証人への請求
自己破産する負債の中に、保証人付きの借金が含まれていると、保証人へ請求がなされます。
迷惑をかけないように、あらかじめ保証人とよく話し合っておく必要があるでしょう。
免責後7年は自己破産ができない
一度、自己破産が認められると、以後7年は、自己破産ができません。
自己破産後に多額の借金を抱えてしまうことには、十分注意しましょう。
自己破産の申立てをする場合、裁判所に提出する書類が多くあります。
また、それぞれの状況に応じて、用意する書類も異なります。
「どの書類を用意すればいいかよく分からない…」という声も耳にしますが、破産手続きをご依頼頂いた場合には、個々の状況に応じて必要書類のご案内を行います。
また、破産の申立書などは、こちらで用意を行っていきます。
必ず必要になる書類
・自己破産の申立書一式
・収入印紙や予納郵券と債権者宛の封筒
・給与明細2ヶ月分
・住民票(本籍・続柄・世帯全員記載の申立て3ヶ月以内のもの)
・通帳
・自宅の賃貸借契約書(所有の場合には登記簿謄本)
・課税証明書又は源泉徴収票(非課税の場合には非課税証明書)
・公共料金(電気・ガス・水道)の支払いを証する領収書
(銀行口座の通帳から振替がある場合にはその記帳記録で代替可能)
会社関係の書類が必要な場合
・会社に財形貯蓄や社内積立金がある場合にはその証明書
・勤続5年以上の場合には退職金見込計算書
(就業規則などで算定できるなら代替可能)
・1年以内に退職している場合には退職金に関する書類
車を持っている場合に必要な書類
・駐車場の契約書
・自動車を保有している場合には登録証又は車検証と価格の査定書。
(登録後6年以内で残ローンがない場合には購入時の見積書など)
不動産で必要になる書類
・過去に不動産を相続したことがある場合にはその登記簿謄本
・過去2年内に不動産を売却している場合にはこれを証する書面
・不動産を任意売却している場合には抵当権者の領収書及び売買契約書
その他必要になる書類
・保険に加入している場合には保険証券とその解約返戻金計算書
・株式やゴルフ会員権を保有している場合にはそれを証明する書類
・離婚をしている場合には、養育費や慰謝料などの支払いの分かる書面
・申立人が自営業者又は会社代表者の場合にはこれに付随する書面
ホームページの執筆者
司法書士法人かながわ総合法務事務所の代表。2008年より司法書士登録。
債務整理を専門とし1万件以上の事案を解決してきました。こうした経験を記した「債務整理の専門家ブログ」は多くの方に好評を頂いております。
債務整理のことなら当事務所にお任せ下さい。日本全国の方に無料相談を行っています。
債務整理の無料相談はこちら
「優しく」「親身に」「安全な債務整理を」ご相談者のみなさまが、安心して進められる手続きをご提案します。
- 任意整理の和解実績1万件以上
- 日本全国で無料相談に対応。
- 家族・職場に秘密の方もご安心を
- 電話・メール共にご相談は無料
- 電話相談は予約不要。すぐにOK
- 今月の返済が難しい場合も大丈夫!